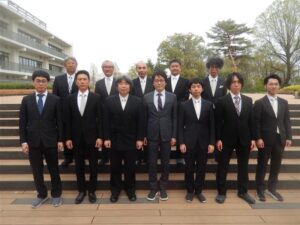2025年度 高校入学式が挙行されました。
TOHO Today高校
さる4月8日(火)に高校入学式が行われ、82期高校1年生の312名が入学しました。
□
□
桐朋中学からの進学者に加え、新たな仲間も加わりました。
□
式では、歓迎演奏も披露されました。
□
□
以下に、入学式で新入生に向けて語られた「校長の言葉」をご紹介いたします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ここ国立も、桜をはじめ春を彩るさまざまな花が咲き誇り、木々も柔らかに緑をまとう。まさに春爛漫といった言葉がぴったりの美しく、色あざやかな景観となっています。生命の輝きに充ちた本日、新入生の保護者の方々にご臨席を賜り、桐朋高等学校の入学式を挙行できますことを大変嬉しく、有り難く感じております。
新入生のみなさん、入学おめでとう。高校生としての第一歩を踏み出しました。今、どんな気持ちですか。少し大人びた気分を楽しみながら、晴れやかさ、誇らしさを感じている諸君が多いことと思います。
保護者の皆様方、ご子息の桐朋高等学校へのご入学、誠におめでとうございます。ご子息の健やかなるご成長に寄与すべく、第82期高1学年の教員ともども、精一杯取り組んでまいります。何とぞ私たちの桐朋教育に温かいご理解とご支援を賜りますよう、高いところからではございますが、心よりお願いを申し上げます。
さて、新入生のみなさん。昨年10月、こんな新聞記事にぼくは強く関心を持ちました。「AIは分断を埋められるのか?」
人工知能(AI)を司会役に立て話し合いをすると、相互理解が進み、社会の分断を改善することができるという研究成果が報告されたのだそうです。研究したのは情報工学者の伊藤孝行さん。伊藤さん、世界中の紛争解決に役立てたいとの思いで、AIの開発に取り組み、一定の成果を収めています。
そのAI。敵対する関係者が話し合う際、司会者や仲介役となって、1人ひとりの意見を吸い上げ、話し合いが円滑、かつ、有益に進むようファシリテートする力を持ったAIです。
こんな実験もしています。アフガニスタンで、対立している3つの部族から無作為に選んだ参加者128名をグループに分け、ネット上のチャットルームで議論してもらう。取り上げたテーマは、避難民の問題などアフガニスタンが直面している課題。その議論を、AIがファシリテートするグループと、AIなしのグループで行い、議論の前後で、他部族に対する不安や偏見がどう変化したか。心理学テストで確認しました。すると、AIが仲介したグループの参加者は、AIなしより、不安や偏見が統計的に明らかに小さくなったのだそうです。伊藤さん、こう分析しています。
「AIのファシリテートだと、なぜ理解が深まるのか。議論が活発になって、見通しもよくなるからだと考えています。参加者が増えると、人間は議論全体の把握が難しくなるのに対し、AIなら多くのアイディアや意見が出ても対応可能だし、発言内容もかなりの精度で読み取ることができる。議論への対応力が上がるよう、AIにこんなシステムを構築しました。発言を問題、アイディア、賛否の3つに分類し、それぞれを関連づける樹形図を作って整理する。すると、ポイントとなる意見や多くの人に共通する考え方などが浮かび上がってきて、議論を整理し、前に進めることができる。さらに、AIは発言の中身には踏み込まず、議論を整理し進める発信だけをするので、アフガニスタンでも、日本でこうした実験を行った際も、AIのファシリテーションは、人に任せるより公平だと評価いただきました。もう一つ、こんなデータもあります。人のファシリテーションよりAIの方が発言が1.6倍に増え、さらに、人とAIが協力してファシリテートすると、発言は2.7倍にまでなったのです」
伊藤さん、こうした研究に取り組む理由について、こう語ります。
「協力関係のある集団は優れた知性を発揮する、そんなコレクティブ・インテリジェンスに関心を持っています。3人寄れば文殊の知恵。多くの人が意見を出し合えば、すばらしいアイデアが得られると信じているのです。すぐに多数決で決めればいいのではなく、民主主義は議論こそが大切。いろんな意見が集まるよう議論し、全体の課題を明らかにしたうえで、多くの人が納得感を持てる決定を下す。社会課題と向き合う際、こうしたアプローチへの期待が高まれば、分断や紛争は自ずとなくなっていくはずです。それを目標にAIの研究を続けています」
新入生のみなさん。桐朋は、自分から動き、自分たちで創り上げる自主性を大切にしていて、意欲的に取り組む中、逞しく、凜々しく成長していく諸君がたくさんいます。さらに、一人ひとりの個性や考え方を尊重し、それぞれの力を結集することで大きな成果を遂げる学校でもあります。その土台が、活発な意見交換、納得づくで事を進められる意思疎通だと思いますし、伊藤さんが強く関心を寄せるコレクティブ・インテリジェンス、集団だからこそ発揮できる知性を活かせているからだと考えます。
82期のみなさんがこれからの話し合いで、どう議論をファシリテートし、82期ならではのコレクティブ・インテリジェンスを創り上げて、いくのか。期待していますし、大いに楽しみにしています。
社会の分断に対し、別のスタイルでアプローチしている人をもう1人紹介します。アメリカで活躍しているスタンダップ・コメディアン、柳川朔さん。
スタンダップ・コメディアンとは、マイク一本で舞台に立ち、ジョークで観衆を沸かすコメディアンのこと。柳川さん、キャリアは15年を越え、シカゴを中心に全米各地で、さらには世界10カ国も巡りながら、笑いを届けるべく奮闘しています。
その際のモットーは、自分の視点で笑いを届ける。普段生活する中で多くの人が見過ごしてしまうことを、彼らとは違う角度、自分ならではの視点で笑いにして伝える点を心がけているとのこと。柳川さん、こう話します。
「思うに、いいジョークとは、ぼくが言うからこそおもしろいジョークだと思います。彼が言っても笑えないが、ぼくという人間の口から発せられることでその意味が増し、おかしみが生じるものこそ、奥行きのあるジョークとなるのです。だから、いいジョークを作るには、自分は誰なのかを知っていないといけないと考えています」
新入生のみなさん。高校という時期は自分を形作る大切な時期です。柳川さんが語る、自分が誰かを知るのは、みなさんにとっても重要なこと。自分を客観的に見つめ、自分の持つ力や長所を実感できれば、自分をいっそう活かし、納得感ある自分を創ることができる。さらに、さまざまな人とふれ合い、自分が気づいていない自分を知る、見出すことも重要だと思います。個性豊かな桐朋生たちと、クラスメイトはもちろん、上級生とも積極的に交流し、学外の人とも接点を持つ。さらには、読書や映画などフィクションの世界でもさまざまな人に触れながら、自分を見つめ、自分を知る機会を、自分から創ってほしいと願っています。
さらに、スタンダップ・コメディの意義を柳川さん、こうした点にも見出しています。
「移民が集まる中でできた多民族国家、アメリカ。アメリカの地でジョークが成してきた役割は、他者に自分が敵でないことを示すことだったとも言われています。文化を異にする両者がジョークを通して歩み寄ることで、あなたの敵ではないですよと示し、関係を構築してきたのだと思います」
このジョークの持つ意義がいっそう高まる。今のアメリカはそんな状況です。社会の分断は、大統領選挙を見ても、アメリカ社会がずっと抱え続けている人種差別の問題においても、深刻さが見て取れます。そんなアメリカで笑いを生むスタンダップ・コメディアン。日本との違いを、柳川さん、こう説明します。
「日本のお笑い芸人がテレビというお茶の間と地続きの媒体で、視聴者から親しみやすさを求められているとしたら、アメリカのコメディアンはむしろ、思想を求められているのかもしれない。なぜなら、コメディはいつの時代も社会を真正面から映してきたから。日々のニュースがその日の夜にはネタになり、社会への人々の関心がそのまま笑いに昇華される。それがスタンダップ・コメディなんです」
さらに、柳川さん、こんなやり甲斐も語ります。
「自分と同じ意見の客しかいない舞台で、そうだ、そうだと共感されることにぼくは意味を感じません。スタンダップ・コメディの本質は、意見の違う人をも笑わせること。このクリエーティブに懸けるところがやり甲斐だし、好きなんです。人類にとって笑いが敵でないことを表明する手段なのだとしたら、さまざまな人が同じテーマに対し、笑いを共有している空間って、なんて平和な場なのだろうと思うんです。笑いを通せば、深まる分断を乗り越える対話のきっかけとなる。分断を少しでも癒せるなら、舞台に立ち続ける意義がある。ぼくはそう思っています」
新入生のみなさん。柳川さんの「分断を改善したい」、「多様性が尊重され、誰もが誇りを持ってイキイキと暮らせる社会にしたい」という思いは、桐朋が大切にしている、お互いを尊重し、認め合う姿勢と大きく重なります。
ご存知の方もいると思いますが、柳川さん、本校の卒業生です。
一人ひとりの個性や考え方を尊重し、それぞれの思いや意図を理解しようと関わりを持つ。こうした関係性があるからこそ、自然体で過ごせるし、自分に自信が持てる。その結果、桐朋生の特徴である個性の輝きが実現するのだと思います。
新入生のみなさん、改めまして、入学おめでとう。82期のみなさん一人ひとりが、自分を深く知ることで自らを創り上げ、そうしたみなさん同士がお互いを尊重しつつ、積極的に関わり合うことで、どんなコレクティブ・インテリジェンスが生まれるのか。大いに期待してますし、楽しみにしています。
高校の3年間を一緒に実り豊かなものにしていきましょう。