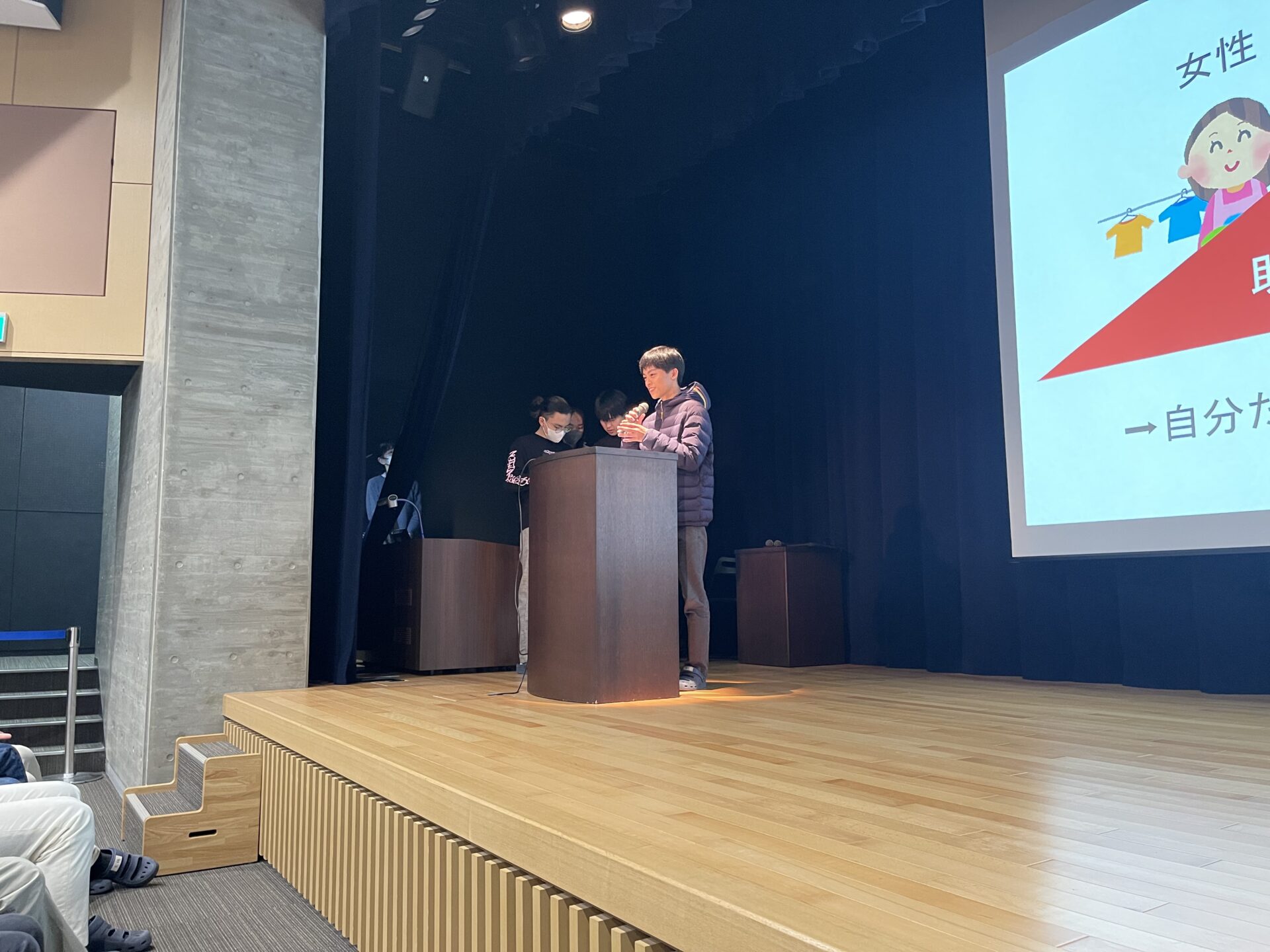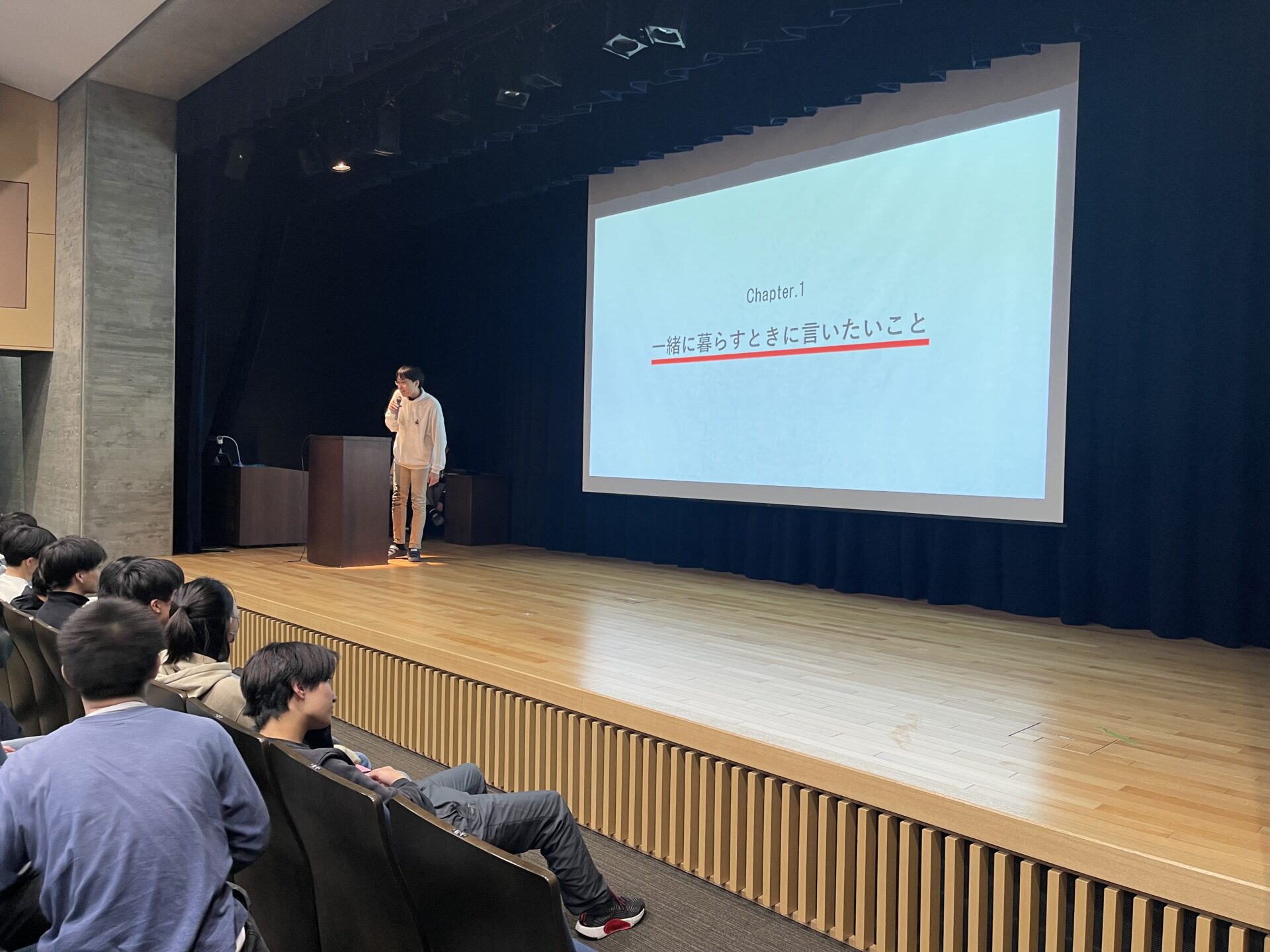高2 【女子部・男子部意見交流会】学年報告会がおこなわれました
TOHO Today高校
毎年高校2年生では、桐朋女子高校との意見交流会を実施しています。家庭科の授業の延長として、「働き方」「ライフスタイル」「結婚観」などについて、同世代の異性の意見を聞き合うことを目的としています。今年も2学期、11月2日(土)に意見交換会が、調布市仙川にある桐朋女子高校で実施され、男子部からは80期高2生の有志17名が参加してくれました。
前もって各校で実施された意識調査アンケートの結果をもとに、授業内で議題をブラッシュアップしてきました。当日の意見交換会では「男性が固定概念にとらわれているのか」「将来仕事をしたいか、家事との兼ね合いをどうするか」「男女の格差を日常で感じるか」「デートの費用を相手に払って欲しいか」「生理の時、女性はどのような対応を必要としている?」などのバラエティー豊かな内容を話し合いました。
そして1月15日(水)6限LHRにて、参加者の皆さんが学年全体に向けて、スライドを利用した報告会を実施してくれました。寸劇など趣向を凝らした発表のおかげで、楽しい雰囲気で学べたと思います。
【生徒(Audience)の感想(抜粋)】
・今日の話を聞いて女性に対する認識が変わったと思う。自分の中で「男女の偏見は駄目」という考えがあったが、話を聞く中で「自分が自然と偏見を持っていたのでは」という見方ができるようになり、聞いていてとても学びになった。(A組)
・自分主体で(家事などを)やる意識がない人が多いと思った。「ありがとうと伝える」と言っても、言うだけではなくてやる、実際に行動した上で言わなければ意味はないと思う。(A組)
・僕は桐朋小出身なので桐朋女子とは関りがあると思っていたが、報告を聞いて、思っていたことと全然違って驚いた。生理のことはあまり気にしなくて良いそうなので少し安心した。将来的には、僕が優先的に(家事を)やりたいと思う。(A組)
・思っていたよりも互いの意見をすり合わせた実践的な話を聞けて、思い込みやおせっかいで動いてはいけないということや、自分にできること、やりたいこと、相手のできることやりたいことを考え、話し合って行動することが大切だと分かった。「ありがとう」と「ごめんなさい」は大事!(B組)
・全員難しい心持ちで行ったのではないかと思うが、それぞれの班が話し合いでちゃんと話し、自分たちの疑問を解消して帰ってきてすごいと感じた。家事や仕事の議題は、男女の認識のズレや個人間の差を改めて確認した。パートナーとはコミュニケーションをしっかりとって、お互いに納得のいく結論を、どんな話題でも先につくっておくことが必要だなと思った。(B組)
・最後の先生方のお話が、実態をともなうもので生徒たちとは違った、より現実味のあるもので面白かったです。自主的に参加した生徒による発表だったので、情熱を感じます。(C組)
・普段は滅多にすることのない話題を議論するのはとても良いと思うが、報告発表を聞くと(先生が同席していたということもあり)互いの意見をぶつけ合うということは少なく、共通点をまとめることが多いと感じた。家事分担の負担割合や、男女間の配慮のすれ違い、女性の就職志望率など、思いもよらない女性側の意見が聞けて面白かった。(C組)
・相手が女性だからこうするべき、ということではなく、個人差がやはりあるので、一人一人に合った対応を互いにしていくのが、男女平等への第一歩であると考えた。(D組)
・一番議論された議題は「家事の分担」だったように思えます。その中でも日頃から感謝を伝えようという言葉が印象に残りました。一人の受験生としては女子枠というのはいただけないと言いますか、「一時的な措置」にしても、当然根本的な対策が必要なのではないかと思います。(D組)
・桐朋女子に行って生理について聞いた勇気がすごいと思う。女性の生理との向き合い方はとても難しいものだと思っていたが、人それぞれに対して考えてあげないといけなくて、さらに難しく感じた。(E組)
・異性間において価値観の違いを前提にした討論と言うのは、非常に難しいものだと思っていたが、互いに意見を交わして建設的な議論がなされていたので、とても有意義だと思った。結局のところ、問いに対する答えが、同性であっても人によって千差万別だったので、価値観の違いは性の違いよりはむしろ個人差に依存することを改めて認識させられた。今なお、男女間の格差問題は盛んに議論されているが、一番大切なことは、お互いの特性を理解して問題に対する解決策を社会全体で考えていくことである。家庭においても同様だ。互いに理解し合うことが我々の暮らしの幸福へと繋がると思った。(E組)
・僕はよく母親から「早く孫の顔が見たい」と言われるのですが、今回の話を聞いて、女性と付き合う上で一番大切なことは、自分の価値観で行動をするのではなく、相手の気持ちを尊重しながら共に行動することだと考えました。(F組)
・周りの大人の話を聞いていると、自分の想像よりも共同生活が大変だったり、人間として終わっている人も多いと感じることが結構あります。自分が大人になったとき、そういう大人になってしまうのではないかという恐怖を忘れないようにしていきたいです。(F組)
・今までの中高5年間を通して同年代の女子と今回のように話す機会は無かったので、交流会に行くことができなかった身として、実際に参加して討論をしたかったなあと思った。将来的に役立つ情報になりそうなものも聞くことができたため、とても良いイベントだと思った。(G組)
・女子との関係を構築することにおいて、協力が大事であるようなことが言われていたが、そもそも自分が結婚できるかが不安なため、まずは自分磨きをしようと思った。(G組)
・夫婦の家事・労働の比率について、どうしても「男女平等を配慮しなければ」という思考が湧いてくるが、男女関わらずただ二人の同居人であるという気持ちで取り組んだ方が良いと考えた。(G組)
・いくつかの班で共通して、男子部は「家事を分担したい」とした人は多いが、実際の家事内容への理解が浅いのではないかという女子部からの指摘があったと報告していた。確かに自分自身も詳細な分担方法は想像しにくく、他にも同じような人はいると思う。僕自身は、相手との相談を重ねそれぞれが最低限納得する分担方法を模索することが大事だと思った。(G組)
【家庭科の教員より】
交流会に参加してくださった代表者のみなさん、報告会の準備と実施にも尽力してくれて、本当にありがとうございました。また、報告会を聴講した学年のみなさんからも印象的なコメントが多数寄せられ、学年全体で意見を共有しようとする空気が作られていました。
この交流会は開催されるようになり20年以上となります。その間に社会におけるジェンダー観は様変わりしてきたと言えますが、個々人が抱えたり、感じたりしているジェンダーにまつわる問題がすべて解決してきている、とは決して言えません。
発表の中でKくんが「男子校だからこそ、同世代の異性どうしで議題に対してよい距離間でディスカッションできた。」とコメントしているのを聞きました。異性の存在はジェンダーに関する問題を探求する同志のような存在である、とも言えるのだと感じさせられる意見です。すぐには役立つものではないかもしれないけれど、必ず今回の経験や意見が近い将来につながることを願っています。